「うちの子、最近サッカーで伸び悩んでるかも…」
そんな不安を感じたことはありませんか?
試合で活躍できないと、つい焦ったり、
「親としての関わり方が間違ってるのかも」と悩んだりしますよね。
でも安心してください。
サッカーで伸びる子の親には、いくつかの共通点があるんです。
私は、小学生サッカーを約10年指導してきた中で、
グングン成長する子の家庭には“親の関わり方”に違いがあると感じてきました。
たとえば、週末に子どもと一緒にプロの試合を観て、
「あのパスすごいね!」と会話するだけでも、学びとやる気が変わってきます。
最近では、スマホ1つで世界中のトッププレーが観られる時代。
私のおすすめは「DMM×DAZNホーダイ」。
一緒に観るだけで、親子の会話も自然と広がります。
そんな時間こそ、「ちゃんと考えてる親だな」と思われる一歩になるんです。
親の接し方が変われば、子どもの伸び方も大きく変わります。
この記事では、伸びる子の“親の特徴”と、
ついやってしまいがちなNG行動、今日からできる関わり方のコツをまとめました。
お子さんの未来のために、「できる親」の一歩を、今ここから始めませんか?
~当記事はこんな人におすすめ~
- 小学生サッカーの母
- 伸び悩みに不安な親
- 周りの成長が気になる
- 親の関わり方に悩む
- できる親と思われたい

子どもが試合で活躍するためのサポートを学ぼう!
⇓家族でサッカーもエンタメも楽しめる
うちの子だけ伸びてない…?
「どうしてあの子だけうまくなってるの?」と感じたことはありませんか?
子どもの成長に差が出始めると、不安や焦りが出てくるのは自然なことです。
ここでは、そんな気持ちとどう向き合えばいいのかをお伝えします。
周りの成長が気になるのは“当たり前”
周りの子と比べてしまうのは、自然な感情です。
なぜなら、成長の差が見えるのはサッカーの世界ではよくあることだからです。
特に小学生のうちは、数ヶ月で技術や体格がガラッと変わることもありますよね。
たとえば、こんな場面で不安を感じやすいです。
- 同じ学年の子が試合で活躍
- レギュラーに選ばれた子がいる
- SNSで他の子の活躍を見る
私も指導の現場で、そうした声を何度も聞いてきました。
でも大切なのは「今の伸び」より「これからの伸び」です。
焦らずにわが子のペースを信じてあげることが、長い目で見て大きな力になります。
伸びるタイミングは人それぞれ
伸びるタイミングには、子どもごとに差があります。
その理由は、体の成長や心の発達には個人差があるからです。
小学生のうちは「今は目立たなくても、あとで一気に伸びる子」も多いんですよね。
実際、こんなケースはよくあります。
- 高学年で急に走力アップ
- 低学年では控えだった子が主力に
- きっかけ一つでプレーに自信がつく
私の教え子にも「4年生までは試合に出られなかったけど、6年生で中心選手に」なった子がいます。
大事なのは、“今すぐ”ではなく“長く育てる”視点を持つことです。
焦らず信じて見守ることで、子どもはしっかりと伸びていきます。
焦りや不安こそ親としての“本音”
焦りや不安を感じるのは、子どもを想う親の“本音”です。
子どもが思うように活躍できないと、親の方が落ち込んでしまうこともありますよね。
周りの子と比べてしまうのも、頑張ってほしいという気持ちの裏返しです。
実際に、保護者からはこんな声をよく聞きます。
- 試合に出られなくてつらい
- うちの子だけ上達が遅い
- 声をかけるたび空回り
私も現場で、悩みながらも子どもを支える親の姿を何度も見てきました。
でも、そうした感情こそが“ちゃんと向き合っている証拠”なんです。
大丈夫です。完璧である必要はありません。
焦る気持ちを否定せず、まずは受け入れることから始めてみましょう。



次の章で、具体的な3つの
関わり方をご紹介します。
「伸びる子の親」がしている3つのこと
子どもの成長には、親の関わり方が大きく影響します。
実際に、グングン伸びていく子の親には“ある共通点”があるんです。
ここでは、そんな親たちが実践している3つの関わり方をご紹介します。
ポジティブな声かけで心が育つ
ポジティブな声かけは、子どもの心を大きく育てます。
言葉は、子どものやる気や自信に強く影響するからです。
特にサッカーは、成功と失敗の繰り返しで成長していきますよね。
だからこそ、失敗のあとに「大丈夫!」「ナイスチャレンジ」と声をかけるだけでも、前向きな気持ちが育ちます。
たとえば、こんな声かけが効果的です。
- 動きがよくなってきたね
- 今のパス、良かったよ
- そのチャレンジ、すごくいいね
- 前よりも声が出てたよ
- 最後まであきらめなかったね
こうした言葉が、子どもの「もっと頑張ろう」という気持ちを引き出します。
サッカーの技術だけでなく、心の成長にもつながる声かけを意識していきましょう。
自主性を信じて見守る
自主性を信じて見守ることが、子どもの成長を後押しします。
サッカーは、プレー中に自分で判断する場面が多いスポーツですよね。
そのため、自分で考えて動く力がとても大切になります。
親があれこれ指示を出しすぎると、子どもが考える機会を失ってしまいます。
「どうする?」「自分で考えてごらん」と声をかけるだけでも、考える力が育ちます。
たとえば、こんな場面では見守りが大切です。
- 練習メニューを自分で考える
- 試合でポジションの役割を理解する
- 失敗を振り返って改善する
- 自分の意志で練習に取り組む
- 作戦や目標を自分で決める
子どもが迷っているときこそ、信じて任せてみてください。
自主性は、試合でも日常でも生きる力になります。
「親に信じてもらえた」その経験が、何よりの自信につながりますよ。
試合を一緒に観て学ぶ
試合を一緒に観ることで、学びと親子の会話が深まります。
実際のプレーを見ることで、子どもは多くの気づきを得られますよね。
「すごい!」「あのプレー、うまいね」と声をかけるだけでも十分です。
親子で試合を観ながら話す時間が、学びと信頼関係を育ててくれます。
プレーの意図や動きを自然と理解できるようにもなります。
たとえば、こんな工夫がおすすめです。
- 一緒に好きな選手を見つける
- プロの試合を一緒に楽しむ
- 「あのプレーどう思う?」と聞く
「プロの試合ってどうやって観るの?」という方も安心です。
最近は「DMM×DAZNホーダイ」などで世界の試合が気軽に観られます。
移動中でもスマホで楽しめるので、生活の中に取り入れやすいですよね。
試合を観ることは、親ができる最高の“学びのサポート”のひとつです。



次は、親がやってしまいがちな“NG行動”について見ていきましょう。
⇓親子でサッカー観戦するならコチラ
やってしまいがちな“NG行動”とは?
「よかれと思ってやっていたことが、実は逆効果だった…」
そんな経験はありませんか?
子どもの成長を願う親ほど、ついしてしまいがちな行動があります。
ここでは、伸びる子を育てるうえで避けたい“NG習慣”をご紹介します。
他の子と比べてしまう
他の子と比べるのは逆効果になることもあります。
比べられることで、子どもの自信が削られてしまうからです。
「◯◯くんはもっと上手なのに」などの言葉は、やる気を失わせる原因になりますよね。
たとえば、こんな声かけには注意が必要です。
- 〇〇くんはレギュラーだよ
- あの子は毎日練習してるよ
- 同じ学年なのに上手だね
- あなたももっと頑張りなさい
私自身の指導経験でも、比べられることで意欲を失ってしまった子を何人も見てきました。
比べるのではなく、「昨日の自分と比べて伸びているか」に目を向けてあげることが大切です。
子ども自身のペースを大切にしながら、成長を信じて見守りましょう。
練習に口を出しすぎる
練習に口を出しすぎると、子どもの意欲を奪うことがあります。
理由は、自分で考える力が育たなくなるからです。
サッカーは判断力が重要なスポーツ。親の指示で動いてばかりでは成長が止まります。
たとえば、こんな行動には注意が必要です。
- 家で細かくプレーを指摘
- 「もっと走れ」と繰り返す
- 指導者と違うアドバイス
- 失敗を叱ってしまう
私の指導経験でも、親の助言で混乱してしまった子を何人も見てきました。
「見守る勇気」こそ、子どもが自分で伸びる力を引き出すサポートになります。
口を出すより、頑張る姿を認めて応援する。これが一番の関わり方です。
結果ばかりを求めてしまう
結果ばかりを求めすぎると、子どもの意欲が下がります。
なぜなら、失敗を恐れてプレーが消極的になってしまうからです。
サッカーは成功と失敗を繰り返しながら上達していくスポーツですよね。
特に小学生年代は、成長の途中。
うまくいかないことの中にこそ、伸びしろがあります。
たとえば、こんな言葉には注意が必要です。
- 「なんで決められないの?」
- 「もっと活躍してよ」
- 「今日は活躍できなかったね」
- 「〇〇くんは点を取ったのに…」
私の教え子でも、結果を責められて自信をなくした子がいました。
でも、プレーの良い部分に目を向けるようになってから、積極性が戻ってきたんです。
大切なのは「結果」よりも「過程」を認めてあげること。
努力やチャレンジに目を向ける声かけが、子どもの未来を広げてくれます。



次は、親子でサッカーを楽しむことが、
なぜ子どもの成長につながるのかを見ていきましょう!
親も一緒にサッカーを楽しむ
サッカーが伸びる子の親には、ある共通点があります。
それは「子どもと一緒にサッカーを楽しんでいること」です。
知識や技術がなくても大丈夫。
一緒に観て、感じて、語り合う時間が、子どもの心を育てます。
試合観戦で理解と会話が深まる
試合を一緒に観ると、親子の会話が自然に増えます。
「かっこいい!」「今のすごいね」など、感想を共有しやすいからです。
サッカーに詳しくなくても、楽しむだけで十分なんですよね。
たとえば、こんな楽しみ方があります。
- 上手な選手を見つける
- かっこいいプレーに注目
- ユニフォームを話題にする
- ゴールシーンを一緒に喜ぶ
- 「誰が一番すごかった?」と聞く
「今日は◯◯選手がかっこよかったね!」という一言が、子どもにとって大きな刺激になります。
サッカーの専門的な知識がなくても、会話を重ねることで理解が深まっていきますよ。
大事なのは、同じ時間を共有すること。
親子でサッカーを観るだけで、学びと信頼関係が自然と育っていきます。
DMM×DAZNホーダイで“世界のプレー”に触れる
世界のトッププレーを親子で観る時間が、学びに変わります。
子どもが「あんな風になりたい」と思えるきっかけになりますよね。
とくに最近は、手軽に試合が観られるサービスも増えています。
中でも「DMM×DAZNホーダイ」は、欧州リーグやJリーグなどが見放題。
サッカー好きの親子にはぴったりのコンテンツです。
たとえば、こんな楽しみ方ができます。
- 有名選手を親子で応援
- 迫力のある試合を一緒に観る
- ポジションごとの動きを学ぶ
- ゴールシーンを一緒に喜ぶ
- 世界との違いを話し合う
「DMM×DAZNホーダイ」は月額わずか3,480円で、スマホやタブレットから気軽に視聴できます。
サッカーの話題が増えることで、親子の会話もグッと深まりますよ。
>詳しいサービス内容はこちらの記事でまとめています。


⇓DMM×DAZNホーダイの料金・使い方・登録はこちらから!
「見るだけ」で終わらず、「一緒に楽しむ」ができる今こそ、最高の環境です。
ぜひこの機会に、世界のプレーを“家庭の学び”に変えてみませんか?
一緒に楽しむことが何よりの応援
親が一緒に楽しむ姿こそ、子どもにとって最高の応援です。
応援されている実感が、やる気と自信を育てるからです。
「勝ってほしい」よりも「楽しんでほしい」という気持ちが伝わると、
子どもはプレッシャーではなく安心感の中で力を発揮できますよね。
たとえば、こんな関わり方が効果的です。
- 試合後に感想を伝える
- ミスにも笑顔で接する
- かっこよかった場面を褒める
- 練習の様子をさりげなく聞く
- 一緒に試合を振り返る
私の指導経験でも、楽しそうにサッカーに関わる家庭の子は、プレーにも前向きさが表れていました。
親の「一緒に楽しもう」という姿勢が、子どもの心を育てます。
無理に教えようとせず、「見守り+楽しむ」の気持ちで応援しましょう。



一緒にサッカーを楽しむことが成長に繋がります!
まとめ
サッカーで伸びる子には、親の関わり方が大きく影響します。
正しいサポートが、子どもの自信や成長の後押しになるからです。
焦りや不安があっても大丈夫。
今日からできる小さな工夫が、大きな変化を生み出しますよね。
~記事の要点~
- 比べずに見守る
- ポジティブな声かけ
- 自主性を大切にする
- NG行動を避ける
- 試合を一緒に観る
- 学びの時間を共有
- 応援を“楽しむ”こと
そして、親子で一緒にプレーを観て楽しむ時間は、
サッカーを“頑張りたい”という気持ちにつながります。
「DMM×DAZNホーダイ」なら、スマホ1つで世界のプレーを親子で楽しめますよ。
子どもの目が輝く瞬間を、ぜひご家庭でも体験してみてください。
詳しくはこちらの記事でサービス内容をまとめています。


「できる親」の一歩を、今日から一緒に踏み出しましょう!



あなたの関わり方ひとつで
お子さんの才能はもっと伸びていきますよ!
⇓一流のプレーを見るならコチラから













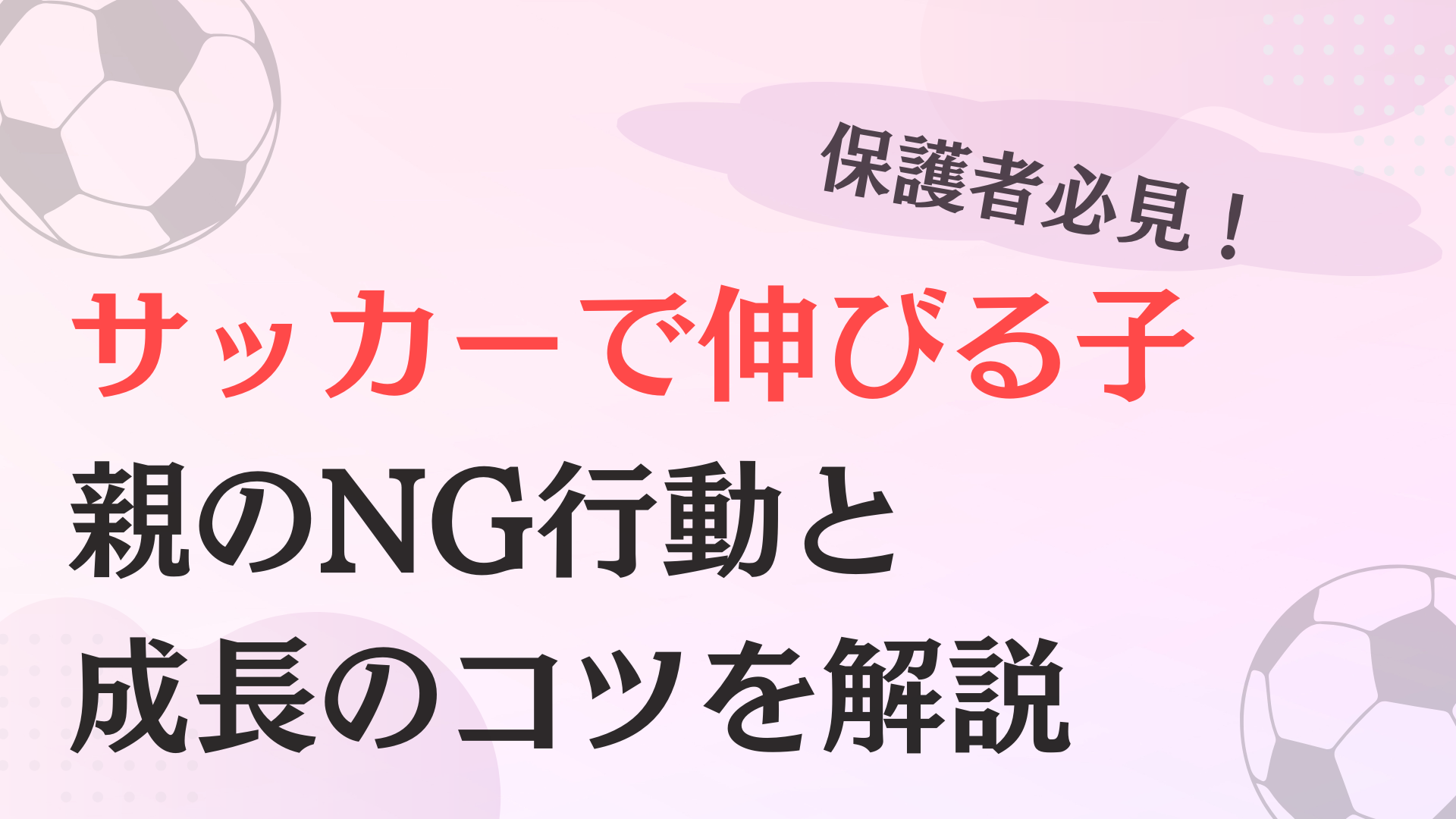
コメント